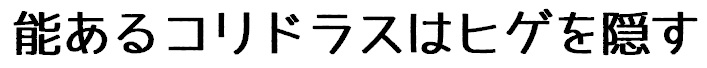水槽に生える苔 (コケ) を食べてくれるオトシンは、水槽内のお掃除屋さんとして人気の熱帯魚です。
私の水槽でも何匹か飼育しており、毎日せっせとコケを食べてくれています。
しかし、オトシンがコケを食べてくれない状況を何度も経験したことがあります。
せっかくコケを取ってくれる魚として水槽に迎え入れたのに、全く働いてくれなかったら、ガッカリですよね…
オトシンがコケを食べない理由として、人口餌の存在やコケの種類などが挙げられます。この記事では、その詳細について紹介していきたいと思います。
オトシンはどんな熱帯魚?
オトシンという熱帯魚には多くの種類がいますが、アクアリウムで最も有名な種類はオトシン・クルスです。
熱帯魚ショップで単にオトシンと呼ばれるのは、このオトシン・クルスになります。

他にもコケ取りとして有名なのがオトシン・ネグロという種類のオトシンもいますが、こちらは、オトシンよりも一回り体が小さくなります。
オトシンは口が吸盤状になっており、水槽の内壁や流木、水草などに吸い付いて暮らしています。そして吸盤状の口で、水槽の内壁や流木に生えるコケを削ぎ取って食べてくれるので、水槽内のお掃除屋さんとして人気を不動のものにしています。
淡水のアクアリウムでは、ヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビと並んでコケを取ってくれる三大巨頭の生体となります。
オトシンがコケを食べてくれない理由
さて、ここからは本題である「オトシンがコケを食べない理由」について、私の飼育経験から原因をお伝えしたいと思います。
せっかくオトシンを水槽に入れたのに、全然コケを食べてくれなかったら…以下の点を注意してみてください。
水槽に生えているコケの種類や状態が原因の場合
オトシンには好きなコケと嫌いなコケがあります。
最も人気のオトシン・クルスについては、色が茶色の茶ゴケを食べてくれません。また、黒髭苔と呼ばれる黒いコケも食べない傾向が強いです。
オトシン・クルスが好んで食べるのは、基本的に緑色をした糸状藻と呼ばれるコケです。水槽の内壁や流木にも生えますが、非常に細いコケのためオトシンも食べやすい種類の藻になります。
下の写真に緑色の糸状藻が発生した石の例を載せておきますが、このように緑色をしたコケであればオトシンが好んで食べてくれます。

もし、皆さんの水槽の中に巨大に成長した藻や苔がある場合、基本的にオトシンでは対処ができません。例えば、上でも述べましたが、水草にこびりついた黒髭苔については、オトシンは食べもしませんし見向きもしてくれません。つついているように見えますが、ほとんどコケの量が減っていないことがわかるかと思います。

人口飼料を与え過ぎが原因の場合
これも大きな原因の一つです。
オトシンは基本的にコケを掃除してくれるメンテナンスフィッシュとしてしいくされるため、他の魚と混泳させる状態が多いです。
その混泳させる魚に与える餌をオトシンが食べてしまうと、オトシンのお腹が一杯になってコケを食べるのを止めてしまうのです。
人間に例えるなら、目の前にセロリとステーキがあったら、多くの方はステーキを食べますよね。それと同じです。
もちろん、オトシンの成長や健康状態を整えるのに、人口飼料は欠かせないこともありますが、あまりお腹が一杯になる状態まで与えてしまうのは良くないと思います。
オトシンは基本的に水槽の底に落ちた人口飼料を食べるので、他の魚が水中で大半を食べてしまうような速度で餌を投入すると良いかと思います。言い換えると、あまり水槽の底に人口飼料が落ち過ぎないようにするということですね。

水槽が明るすぎることが原因の場合
これは全てのオトシンに当てはまることではないのですが、10匹のオトシンを飼育すると何匹かは水槽用ライトが点灯しているときには動かずにじっとしている場合があります。
オトシンはナマズの仲間なので、基本的に臆病です。そのため、暗い場所が好きで夜行性の一面を持ち、水槽のライトが明るすぎる場合には、物陰にひそんだりして動かないことがあります。
そのようなオトシンは、多くの場合、水槽用ライトを消した夜の間に活動してコケを食べていることが多いです。
夜に薄明かりを付けてみて、オトシンが元気に動き回ってコケを食べていたら、問題はない事かと思います。
私の60cm水槽にも6匹のオトシン・クルスがいますが、2匹は昼間に全く動かないです…。夜になると活発に動き出します。
一緒に混泳させている魚の種類が問題の場合
一つ上の見出しで、オトシンは臆病であると記載しました。それに関連して、大きな体の魚と混泳させていると、怖がって動かなくなる場合があります。
私の水槽では、過去にエンゼルフィッシュを飼育していましたが、エンゼルフィッシュが動き回っていると、オトシンはじっとして動かない状態でした。
夜の時間帯になると、エンゼルフィッシュが活発に動かなくなるので、オトシンも安心して水槽のコケを食べてくれていました。
正直なところ、混泳魚が問題という場合にはなかなか打つ手がありません。
オトシンには悪いのですが、動ける時に動いてもらいコケを取ってもらうしかないかと思います。
病気や水質が原因の場合もある
病気の時には、コケだけではなく人口飼料も食べなくなります。
外見上で分かる病気であれば、白点病や尾ぐされ病などがあるので薬浴させて回復をさせてあげて下さい。
ただし、ウイルスや細菌が原因で内臓系の病気に罹っている場合は、見つけることも難しいので、治療が困難になることが多いです。
実はオトシンは水質の変化に弱い面もあります。水槽の水を入れ替える時に、ほぼすべての水を入れ替えるような事になると、動きが悪くなることもありました。一度の水替えの量は、水槽の1/3から1/2くらいにしてあげることも大切な心掛けかと思います。
オトシンがコケを食べてるのにコケが減らない理由
オトシンが頑張って水草や流木に生えるコケを食べてくれているのに、全然コケの量が減らないという場合があります。
多くの場合、コケの生えるスピードの方が早く、オトシンによるコケ取りが間に合わない状態です。
そのような場合には、水槽に入れるオトシンの量を増やすことも一つの手です。
私が管理する水槽を例に挙げると、30cm以下の水槽なら2 ~ 3匹、45cm水槽なら4 ~ 5匹、60cm水槽なら6 ~ 7匹入れています。
少し数が多い気もしますが、水槽内のコケを確実に防ぎたいのであれば、このくらいの量を入れることをお勧めします。
また、コケの成長が早すぎて、オトシンが食べられない大きさに育ってしまっているコケもあります。それらは、オトシンでは太刀打ちできないコケになるので、手で取り除いて除去してあげて下さい。
オトシンを水槽に導入するタイミングに注意
オトシンを水槽に入れるタイミングは、いつが良いのでしょうか?
答えは、水槽を立ち上げてフィルターが立ち上がったらなるべく早い段階で水槽に導入することです。
コケは生え始めの初期に対処をすることが一番大切です。
水槽内でコケが大きく育つと、手に負えません。オトシンを入れようが、ヤマトヌマエビを入れようが、コケの成長速度の方が早くなり、コケ取りの生体ではどうしようもなくなります。
そのため、そうなる前に、水槽立ち上げの初期でオトシンは水槽に入れてあげましょう。
この記事の最後に
この記事では、淡水水槽内のコケ取りとして有名なオトシンがコケを食べてくれない理由について、私の経験から理由を記載させていただきました。
オトシン・クルスが食べてくれるのは、発生初期の糸状藻 (緑色の細い藻) です。また、オトシンはコケが大好きでコケを食べているのではなく、人口飼料の方が好きです。そのため、人口飼料でお腹いっぱいになるとコケを食べてくれないくなります。オトシンを水槽に入れる時は、餌の与えすぎにも注意しましょう。
また、オトシンをコケ取りとして水槽に入れる場合には、水槽とフィルターを立ち上げた後になるべく早めに入れるようにしましょう。コケが大きく成長した状態になると、オトシンは食べてくれません。
コケ取りの生体の習性を知り、水槽内のコケを綺麗にしてくれる飼育環境を考えてオトシンの飼育をしてみて下さいね。